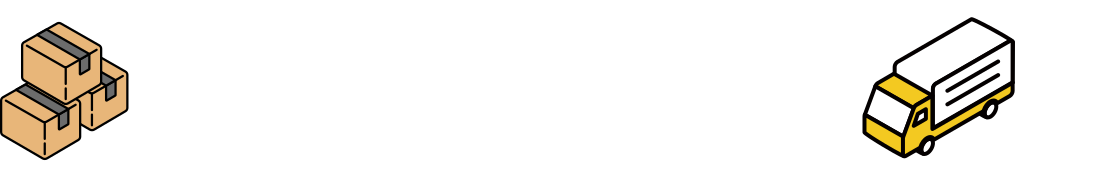電力自由化後の再生可能エネルギーの使われ方はどうなる?

この記事の目次
電力自由化で普及が期待されている再生可能エネルギーですが、その将来像はどうなるのでしょうか。現在と将来について考えてみましょう。
年間平均37,543円節約できます!
エネチェンジ電力比較診断の3人世帯を選択したシミュレーション結果で、電気代節約額1位に表示されたプランの年間節約額の平均値です。節約額はギフト券などの特典金額も含まれています(シミュレーション期間/2025年10月1日~2025年12月31日)

現在の再生可能エネルギーの使われ方とは
再生可能エネルギーには太陽光、風力、水力(小水力)、地熱、バイオマスといったさまざまな種類がありますが、それぞれどんな使われ方がされているのでしょうか。
再生可能エネルギーは熱として利用することもできますが、多くは電気として利用されています。電気は送電線で遠くまで運べる上、安全で使い勝手がよいからです。
自家消費
電気として利用する場合、自家消費される電気もありますが、大部分は、電力会社の系統に接続され売買されています。
全体の電力消費量のうち、どのくらいが自家消費されているのかについては、正確な統計はありませんが、経済産業省の民間企業への委託調査では、1M(1000kW)以下のを設備による電力を自家消費として算出した場合、全体の約2.5%相当という割合が示されています。家庭用の太陽光発電の場合、基本的には自家消費ということですが、余剰電力は電力会社に売電されています。その割合も把握されていませんが、約50%は自家消費されている、というのが一般的な捉え方です。
地域電力会社への売電
再生可能エネルギーの電力は、現在、ほとんどが地域電力会社に売電されています。2012年の固定価格買取制度(FIT)実施以前は、「新エネルギー利用特別措置法」(RPS法)による、電力会社の一定割合の買い取り義務によって、買い取られていました。
いずれも再生可能エネルギーの普及促進を図るのが目的です。現在はFITに制度が一本化され、発電事業者による再生可能エネルギー電力や一般家庭の余剰電力はすべて地域電力会社に売電されています。
新電力による販売
新電力とよばれる特定規模電気事業者は、これまでの電力自由化の中で50kW以上の需要家に電力を供給しています。電力供給の一環として、再生可能エネルギー電力を販売しているところもあります。販売の方法としては、自ら再生可能エネルギー発電所を建設して供給する方法や、グループ企業や他の新電力から調達する方法などがあります。
今後、再エネ電力需要の増大にともなって、新電力による再エネ電力の売買が活発になる見通しです。
再生可能エネルギーの問題点とは
エコロジーなエネルギーとして注目されている再生可能エネルギーですが、安定性など、さまざまな問題も指摘されています。
安定性に課題がある再生可能エネルギー
再生可能エネルギーの一部は自然エネルギーと呼ばれるように、自然条件に発電出力が大きく変動する点が、最大の問題点といえます。再生可能エネルギー電力のうち、特に、太陽光発電、風力発電は自然変動電源と呼ばれ、天候や気象条件に出力が左右されます。
出力の変動を放置すると、電力網全体の周波数変動などといった形で、工場などの生産やコンピュータの作動に悪影響を及ぼしたり、大規模な停電につながってしまいます。
こうした自体を避けるため、出力変動を調整するためには、火力、水力などの調整電源で電力需給のバランスを取る必要があり、再生可能エネルギーのコストを大きく押し上げます。
安定していても、長期的な普及に脆弱性があるエネルギー
再生可能エネルギーには、出力は安定しているものの電源の立地点、燃料の調達などで課題脆弱性を抱えるエネルギーもあります。水力と地熱は、供給の安定性はあるものの、電源の立地点に脆弱性、制約を抱えています。水力は、大規模な開発の余地がほとんどなく、残されているのは小水力という形の、小規模な電源です。
地熱は、環境規制や、温泉地域との地元調整に課題を抱えています。
バイオマス発電は、基本的には火力発電なので立地を問いませんが、その燃料は二次利用的な調達が多く、安定的な原料の確保に脆弱性があるといえます。
コスト負担(賦課金)
規模が小さく、エネルギーの密度が低い再生可能エネルギー電力の発電コストは、火力や大規模水力、原子力などの主力電源に比べてkW当たり2~3倍のコストとなっています。
CO2を排出しない、貴重な国産エネルギーである再生可能エネルギーの普及を図るには、これらのコストの一部を国民全体で負担し、再エネ発電事業を支援する必要があります。固定価格買取制度とそれによる賦課金はその目的のために導入された制度で、賦課金は電気料金のひとつとして徴収されています。賦課金は、電力会社を通じて、発電事業者に再エネ導入促進費用として支払われています。
ライフサイクルコストの課題
地球温暖化対策のためのCO2の排出を評価する場合、ライフサイクルエネルギーあるいはライフサイクルCO2評価(LCA)という言葉があります。
例えば、太陽光発電の場合、発電に伴うCO2はゼロと考えられがちですが、太陽光発電を製造し、それを運搬、据付するときに消費したエネルギーを、LCAでは評価します。そのように、ひとつの製品の原料生産から、製品の生産、輸送、販売に至る全工程(ライフサイクル)における消費エネルギーとCO2を算出するのがLCAの考え方です。
したがって、CO2を排出しないクリーンなエネルギーとを言われる再生可能エネルギーも、LCAの観点からはCO2を排出しているわけです。
LCAを計算すると、太陽光発電や風力発電の1kW当たりCO2排出量は、巨大なダムを作る水力や原子力発電などより多くなってしまいます。これは原子力などに比べてエネルギー密度が低いことや、自然現象によりフル稼働できる時間が短くなってしまうことによるものです。
将来の再生画可能エネルギー
再生可能エネルギーはこれまで見てきたような課題を克服できるのでしょうか。そのために、さまざまな技術開発が行われています。
国が開発を後押しする太陽光発電技術
将来の再生可能エネルギーについては現在、官民で研究開発が進められていますが、国際競争力の観点からとりわけ重要視されているのは太陽光発電の技術開発です。経済産業省のロードマップ(技術開発工程表)によると、現在、火力発電などに比べて大幅に高い太陽光発電の発電コストを2030年までに火力発電並みに引き下げる目標を打ち出しています。つまり、この時点で、太陽光発電は現在の主力電源である火力発電と太刀打ちできるコストになるというわけです。
コスト引き下げには、太陽電池の性能を大幅に向上し、エネルギー変換効率を上げなければなりません。現在主流となっている太陽電池は、結晶シリコンや薄膜シリコン系といわれる電池ですが、将来の電池としては、化合物系や色素増感タイプ、有機系太陽電池などの開発をめざしています。それらが実用化されると、変換効率は現在の20%前後から、一気に40~50%程度に高まり、発電コストの引下げが可能となります。
洋上に活路を見出す風力発電
風力発電については、現在、陸上風力発電が中心ですが、近い将来、洋上風力発電が大きく普及する見通しです。欧州ではかなり普及していますが、四面海に囲まれた日本では、洋上風力発電はきわめて有望視されています。日本近海は、海底が深く、台風などの気象条件も欧州などに比べて厳しいことから、欧州の着床式洋上風力発電とは異なる、浮体式洋上風力発電を実用化する予定です。現在、福島県などで大型の浮体式風力発電の実証試験が行われており、浮体式洋上風力発電が本格的に実用化を迎える時期もそう遠くないとみられます。
蓄電技術による自然エネルギーのバックアップ
再生可能エネルギーの場合は、昼夜や気象条件によって出力が左右されるという問題があります。こうした電気を安定的に使うため、蓄電技術の開発が急がれています。
蓄電池の用途としては、需要家用と系統用の2種類に分けられます。需要家用は、工場などに設置される大型電池から、マンション、戸建住宅用などの小型電池までさまざまです。家庭用電池などは、一部で登場していますが、電池寿命は5~10年と短く、システム単価はkWh当たり10万~25万円といわれます。10時間放充電タイプでは100万~250万円と高額です。将来的には、2030年頃を目途に、寿命20年の、より低コストの電池開発が進められています。
系統用は、発電所や変電所に設置され、発電機能の一部として需要の変動に応じて充放電するタイプです。現在実用化されているのは、寿命が10~15年で、単価はkWh5万~10万円の電池です。2030年頃には、寿命20年と、より長期低コストの蓄電池の実現を目指しています。
発電以外の使い方
再生可能エネルギーの多くは、電気として利用されますが、発電以外の使い方としては、熱や自動車燃料としての利用があります。熱利用としては、太陽熱、地熱などから、直接、給湯、冷暖房用エネルギーとして利用します。バイオマスエネルギーの場合は、多くは燃焼による発電エネルギーとして使われますが、発酵技術によるメタン、エタノール、水素等の生成もあります。エタノールは、ガソリンと混合して自動車燃料として利用されます。メタン、水素等は、燃料電池の燃料としても利用されます。
電力自由化と再生可能エネルギー
電力自由化によって、再生可能エネルギーの普及は進むのでしょうか。
地産地消がやりやすくなる?
電力の自由化によって、再エネ電力に参入する企業が増えたり、需要家が電力会社を自由に選べるようになることで、地産地消型の再生可能エネルギーの普及に弾みがつく、という意見があります。
確かに、再エネは本来、地域密着型の分散電源であり、再生可能エネルギーの地産地消をうたった地域密着型の電気料金メニューなどが提供されるようになると考えられます。しかし、本質的には自由化が進展すると、むしろ広域的な電力利用が進むと思われます。
つまり、東京に住む人が、関西電力から電気を購入したり、北海道の再エネ発電事業者から太陽光発電電力を購入することが考えられます。とくに、自然条件に出力を左右される再エネ電力の場合、出力変動を調整する調整電源、具体的には火力、水力などの電源の確保が重要になります。地産地消型の再エネ電力は、地域内で調整電源を確保することが困難な場合が多いのですが、自由化によって、電力購入の広域化が進むと、地域外の調整電源を幅広く活用することが可能になります。
そのため、自由化、広域化によって、再エネ電力の性格も、地産地消型から、広域電力型に変質する可能性が大きいと見る意見が多いようです。
価格の転嫁はどうなるのか?
「再生可能エネルギーの最大限導入」という国の方針は、当面貫かれる見通しですので、それを担保している固定価格買取制度は、自由化後も維持される見通しです。主力電源の発電コストの2~3倍となっている再エネ発電コストを引き下げるためには、固定価格買取制度が不可欠です。
ただ、買取価格は、低下する傾向にあります。自由化で再エネ発電事業者が事業コストを引き下げることはあっても、発電コストの上昇を価格に転嫁することは考えにくいと思われます。
また課題としては、FIT制度のもと、全ての需要家の負担で下支えされている再生可能エネルギー(FIT電源)の取り扱いが議論になっています。
具体的には、例えば新規参入の電力会社”E社”がFIT電源の事業者の電力だけを買い集めて「100%エコ」とうたったプランを提供したとします。このとき”E社”の100%エコプランの「付加価値」である再生可能エネルギーは、その導入にかかるコストは全需要家で負担しているのに、”E社”が自社商品の特色として謳い、競争上の有利を得ることは不平等ではないのか、といった問題が指摘されてます。
これについては制度設計の現場でも突っ込んだ議論が進められている、というのが現状です。
- 電力自由化後の再生可能エネルギーの使われ方はどうなる? - 2015.7.9
- エコ? 安価? 再生可能エネルギーの特徴を比較してみます - 2015.7.8
- 電力会社のライセンス制から電力自由化が見える - 2015.6.29